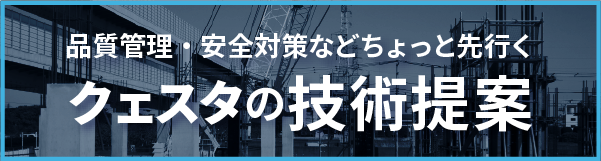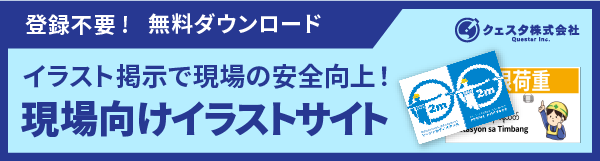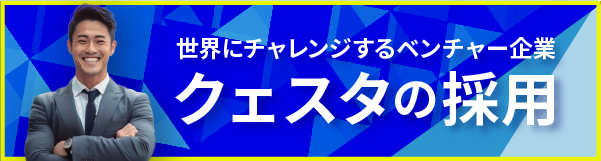NEWS
【出展のお知らせ】建設・建築DX EXPO 2025 夏 東京:貴社の未来を変えるソリューションがここに!
この度、弊社は2025年7月30日(水)から8月1日(金)まで東京ビッグサイトで開催される 「建設・…
クレーム管理を効率化するためのデジタルサイネージ活用術:現場でのトラブルを未然に防ぐ仕組みとは?
小規模建設企業でも導入しやすい最新のテクノロジーとして、デジタルサイネージが注目されています。これを…
この度、弊社は2025年7月30日(水)から8月1日(金)まで東京ビッグサイトで開催される 「建設・…
小規模建設企業でも導入しやすい最新のテクノロジーとして、デジタルサイネージが注目されています。これを…